 院庄林業株式会社
院庄林業株式会社
岡山県津山市でSE構法に使用される集成材を製造する木材メーカー。ヒノキ材・集成材の生産量は国内最大規模を誇る。製材のみならず、山林育成や植林事業にも積極的に取り組み、持続可能な循環型社会づくりを実践している。
※記事中の年数などは取材時のものです。
筆者は家づくりの雑誌やWEBサイトを中心に記事を書く住宅ライターです。様々な工務店や住宅会社の取材を行っています。
そんな私が、「伐採現場を見学しませんか?」とフクダ・ロングライフデザインの福田社長から打診されたとき、抱いたのは「意外」という感覚でした。
なぜなら「伐採現場」という言葉から想起されるのは、丸太の梁がドーンと走り、大黒柱の太さを誇るような家づくり。一方、フクダ・ロングライフデザインの採用するSE構法は、集成材で強度を高め、金物を使って耐震性を確保する、木とはいえどちらかというと工学的なイメージだったからです。
とはいえ見学の機会などめったにない伐採現場。興味津々でお誘いを受けることにしたのでした。
そして見学当日。福田社長の運転する車に同乗し、中国道を走ること2時間余で、岡山県津山市の「院庄林業」に到着しました。車を降りた途端、木の香りと爽やかな空気に包まれて、「わぁ、森林浴の気分!」と深呼吸。そう、そのときはまだ「本物の森林」への厳しい道のりを予想していなかったのです。


津山市内の伐採現場へ向かう一行
伐採現場で日本の林業の厳しさを知る
院庄林業から山の入り口へ車で30分。長靴に履き替えてヘルメットをかぶり、伐採現場へと歩を進めます。前日からの雨でぬかるんだ道に長靴がずぶずぶのめり込み、勾配はだんだん急に。倒れた原木を乗り越える箇所もあり、お気楽な森林浴気分は吹っ飛びます。
途中でクレーン車を器用に操って、原木の枝を落としたり、用途に応じて太さを選別したり、カットしている場面に遭遇。
「ヨーロッパだと無人のトラックが走って無人で切るなど、省力化が進んでいます。ヨーロッパの森林は平地だから、そのまま機械が入って切り倒していけるんですね。日本の森林は山なので、まず伐採現場までの道をつくるところから始めなくちゃならないんです」と院庄林業の社員さん。
時間も手間もかかる日本の伐採。国産材はどうしても価格が高く、運送費を入れても輸入材の方が安いという問題がありますが、その原因の一端を目の当たりにしました。

伐倒から造材までこなすハーベスタ・プロセッサ
さらに息を切らして山道を登り、伐採現場に到着。チェーンソーで木を切る様子を見せてくれるのは、なんと若い女性伐採士さんです。
「大学で学んだ環境学を生かせる仕事がしたいと思い、この会社に就職しました。最初は事務職に配属されていたのですが、入社1年目に伐採士の希望者募集があり、手を挙げたんです」。
重そうなチェーンソーを抱えて軽々とぬかるみ山道を登り、伐採する木のもとへ。うなりを上げるチェーンソーで、一抱え以上もある杉の木のまず片側を切り込み、次に逆側にも切り込みを。体感10分ほどで木がゆさっと揺れたかと思うと、斜面下で見学する私たちの方へドーンと倒れます。もちろん、危険がないほど十分離れているのですが、なかなかスリリングな体験でした。
「私で半日50~60本、ベテランの人なら200本くらい伐採します。危険なことも結構ありますね。切る木と別の木に蔓が絡んでいて、引っ張られて倒れてきたり、重機を扱っているときに、木の重さに耐えられなくて前のめりに倒れそうになったり。だから常に神経を張り詰めています」。
それでも現場にいると、高齢化や人手不足など、林業の問題が具体的に見えてきて、環境学で学んだことも視点が変わってくるとのこと。「ずっと山に関わる仕事をしていたい」と語る笑顔に、林業の未来への光を見ました。

手際よく木を切り倒す女性伐採士


機械で加工した木材を人の目と手で丁寧に検品する
機械化の中に人の目と手が生きる製材工場
本社に戻って工場見学です。丸太から板材にする製材工場と、板材を張り合わせて集成材をつくる工場。どちらも広大なスペースの中、長い木材がベルトコンベアで運ばれながら形を変えていきます。
カットしたり接着剤を塗布したりプレスしたり、もちろんオートメーション化が進んでいてそれにも目を見張るのですが、そんな中でたとえば、年輪の詰まり具合を見て強度を判断したり、集成材に使える木か使えないか、最終的に人が選別するなど、人の目と手が重要な役割を担っていることに感銘を受けました。
使えなかった部分は粉砕してチップにし、バイオマスとして利用したり、固めてボードにするなど、すべてを使い切ります。「山の恵みをわずかにも無駄にしない」との思いが貫かれているのですね。
工場の外には「私のSDGs」という掲示物が。社員1人1人の顔写真とともに、「ゴミの分別をする」「食品ロスをなくす」など自分の目標を掲げていて、微笑ましい気持ちになるとともに、SDGsを身近に感じるいい取り組みだなと思いました。

細かく粉砕し再利用される端材


ハウスで種から育てられるヒノキ
難しい苗木の育成に取り組む理由は
最後に苗木畑を見学しました。ヒノキの種を選別して植え、ビニールハウスで3年間丹念に育成し、成長した苗を背負って山に植えに行く。まさに「森林サイクル」のスタート地点です。
「ヒノキは発芽率が20%ほどという低さ。しかも当初は畑に蒔いていたので、動物やタカに狙われるなど、試行錯誤の繰り返しでした」。
もともと苗木は業者から購入していたのですが、その業者が徐々に減少しているとのこと。「木を伐採すれば、植えなければ足りなくなる。業者が減っているのなら、自分たちで取り組もう」という、シンプルながらも高い志で苗木の育成が始まったのだそうです。

この苗が成長するのに半世紀以上かかる
豊かな森林資源を生かし、大地を育てる
ヒノキの豊かな岡山で、製材業として創業した院庄林業。乾燥の技術に力を入れ、集成材に取り組むなど、常に一歩先を見据えて事業を展開してきましたが、2015年には未知の世界ともいえる伐採に参入します。
「日本では木材市場で原木を買うのが一般的ですが、世界では山を買って自分たちで切るのが標準。市場を通すとどうしてもコストが上がりますから、コストを下げ、地元のヒノキをもっと使ってもらうために、自分たちで伐採をやろうと考えたんです」。
日本は世界でもトップクラスの森林資源を有する国。しかも第二次世界大戦後に植林したヒノキが、今まさに伐採の適時になっています。
「ヒノキは50~60年経つと強度が強く、使用に適した状態になります。また若い木の方がCO2の吸収量が多いので、この時期に伐採することが大切なんです」。
一部の木を切る「間伐」も、周りの草葉の根を張らせて土砂崩れを防いだり、日光を届けて大地を育てるために重要なのだそうです。

美しい年輪に長い時間が刻まれている
循環の底に流れる、ロングライフの思想
苗を育て、植林し、伐採してまた植える。そんな「森林サイクル」を回すことが、山を守り、地球環境を守ることに繋がる。また厳しい伐採現場状況の中でも、作業を合理化し、コストを下げる努力によって、国産材の利用が促進され、それも山の保全に繋がる。
大きな循環の底には未来への視点、「ロングライフ」の思想が流れており、それがフクダ・ロングライフデザインの目指すものと共鳴するのだと、実感した1日でした。

伐採、製材、そして植林、そのすべての工程を自社で行う院庄林業
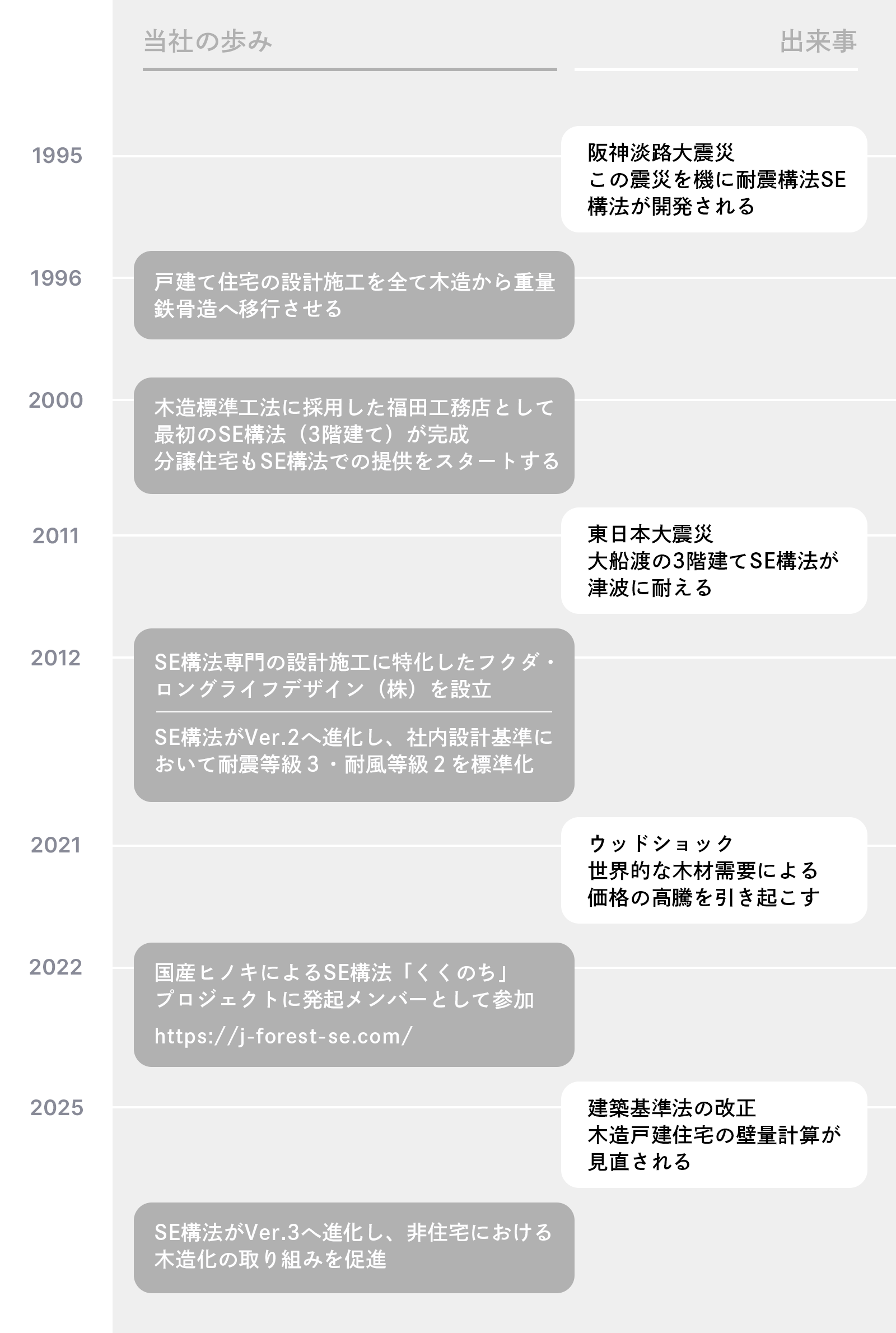
「意外感」から始まった取材でしたが、終わってみると全く違和感なく、福田社長の意図に深く納得しました。「ロングライフ」という一致点はもちろん、それを具体的に実現するための企業努力。SDGsや地球環境問題を単なるお題目ではなく、きちんとビジネス視点を持ちながらクリアしようとする姿勢など、両社に共通する印象を受けました。また女性がナチュラルに生き生きと活躍されている様子にも感銘を受けた取材でした。