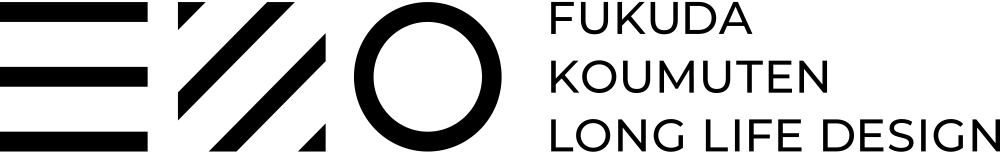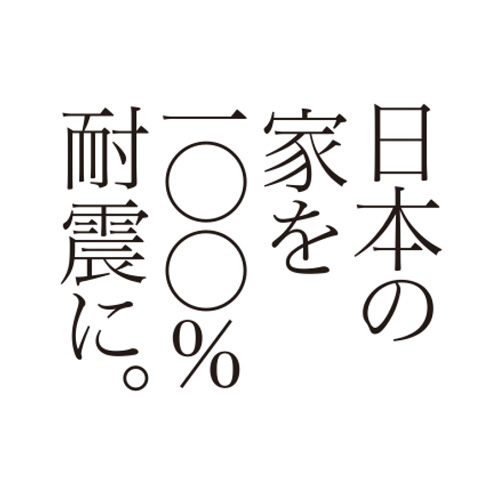こんにちは。工務の大塚です。
先日、(一社)日本建築協会主催の勉強会に参加してきました。
大手建設会社の技術部の方を講師に招いて、午前9時から午後5時30分まで1日かけての勉強会でした。
内容は施工計画と仮設見積りについて、
・品質を確保し、安全で効率よく経済的に工事を進める鍵を握る施工計画の要点を解説。
・仮設工事費は非常に把握しにくい面があるが、施工計画に基づいた合理的で迅速な見積り方法の解説。
なかなかお堅い内容です…ものすごく凝縮して言うならば、
施工計画とは、工事を円滑で安全、正確なものにする為の事前調査、協議、計画などを行う事を指し、仮設見積りは最終的には残らないが、工事に必要なものを合理的に見積りするには?という事を学んできました。
鉄骨(S造)、鉄筋コンクリート(RC造)の大規模建築物を対象とした講義内容でしたが、木造建築に置き換えてもあてはまる事例もあり、改めて知識の整理と再確認ができました。
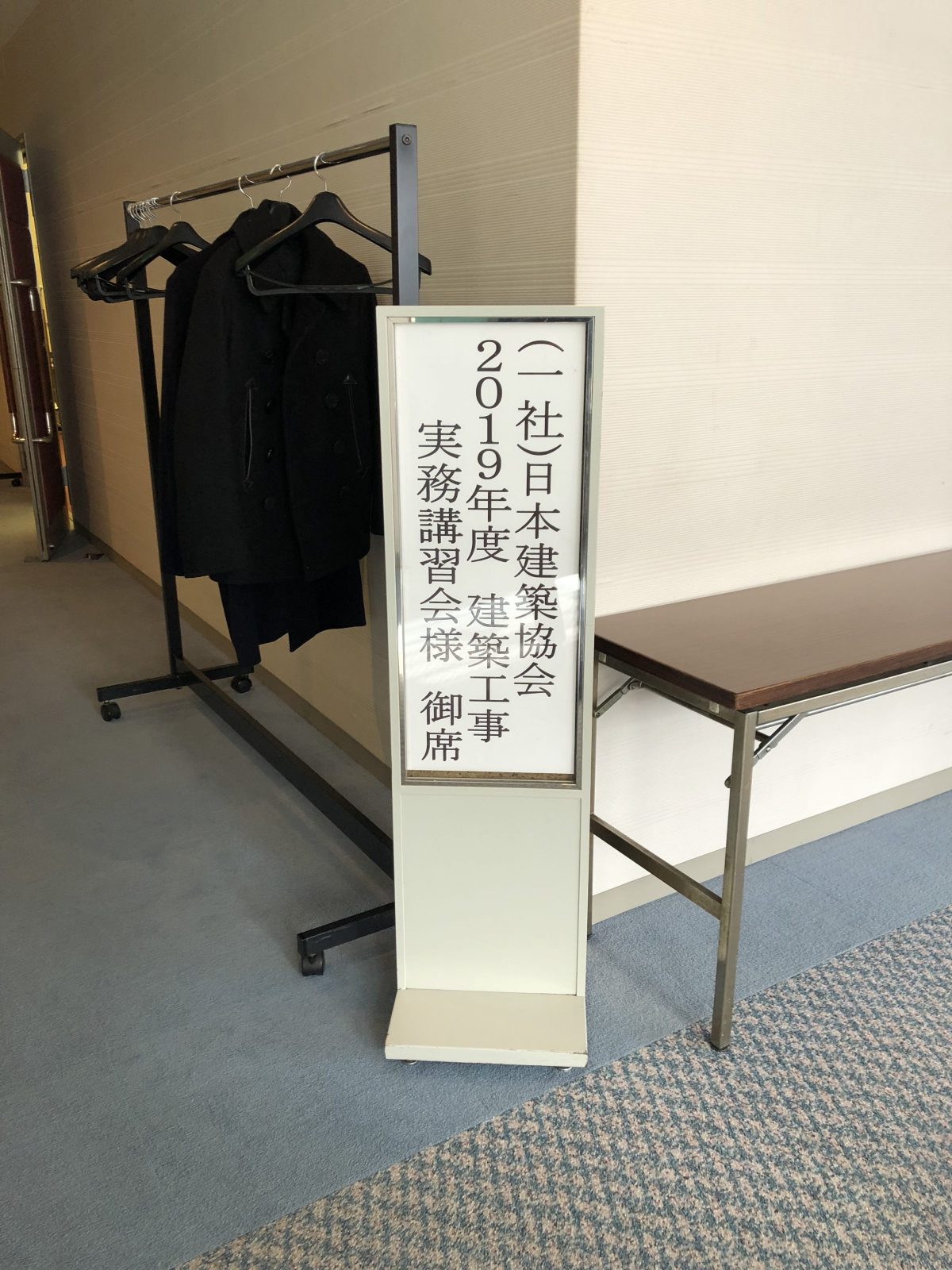

社会人になりたての頃、当時の職場の上司から教えてもらったことがあります。
「現場は生き物。毎日の変化にどう対応するかによって現場の出来が変わってくる」
現場がスムーズに進むように、計画・工程・手配・チェックを繰り返し行っていても予想外の事が起きる事もある、それが現場というものです。分かりやすい例えで言うと、天気予報が外れ作業が進まず、予定していた工期内に終わらない…とか、他社の仕事が急遽割り込んできて、今週は現場に入れない…などなど。関わる人間の数が多いほどこういった事が複合的に発生するときもあります。
じゃあ、そこは置いといて次に進もうとはならないのが建築の難しい所…
現場は生き物だと痛感した経験は何度もあります。
現場で私たちを見かけないときは、工程の調整に追われているのだなと思って頂ければと(汗)
しかし、そんな予期せぬ事態にも各工程と工程の間に余白を作っておく事で後工事の遅延なく進める事ができます。異なる職種の間の工程上の予備日なので、この存在を知っているのは監督だけかもしれません。余白を上手に活用しうまく舵取りできた時は心の中で小さくガッツポーズです(笑)
【個別相談会(オンラインも可能)】
家づくりに悩んだら、フクダ・ロングライフデザインにご相談ください!
性能やデザインのことはもちろん、資金計画や土地探しまで、
家づくりに必要なすべてのステップをサポートします。
(土地探しや物件探しのお手伝いもしております)
詳しくはこちらから→個別相談会
【開催予定イベント・セミナー】
私たちと一緒に家のことを学びませんか?
これから家づくりをはじめる方おすすめの「家づくりアカデミー」や、
「家の裏側がみることができる構造見学会」「完成見学会」「お住い拝見見学会」
など様々なイベントを企画しております。ぜひご参加ください。
詳しくはこちらから→開催予定イベント・セミナー
【資料請求・お問い合わせ】
コンセプトブックや各種パンフレットお送りします。
ご意見やご質問などお気軽におよせください。
詳しくはこちらから→資料請求・お問い合わせ
耐震構法SE構法と無垢無添加による
「パッシブデザイン&リアルZEH」の家づくりを提供する設計工務店です。
新築の注文住宅や既存戸建て住宅の「性能向上リフォーム」、
中古マンションの「木のマンションリノベーション」にも取り組んでいます。
さらに、専属スタッフにより「土地探し・物件探し」もサポート致します。
大阪・神戸・奈良で、土地探し・物件探し、新築注文住宅、
リフォーム・リノベーションをお考えの方はお気軽にお問い合わせ下さい。
フクダ・ロングライフデザイン株式会社
〒553-0003 大阪市福島区福島8丁目17番14号
フリーダイヤル:0120-965-830
https://www.fukuda-lld.jp/