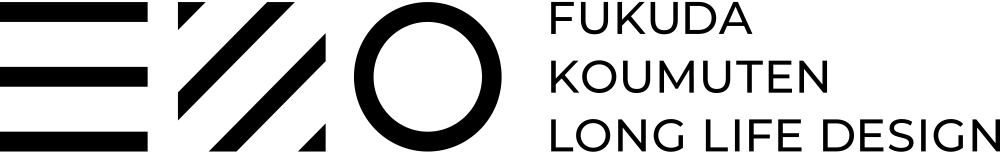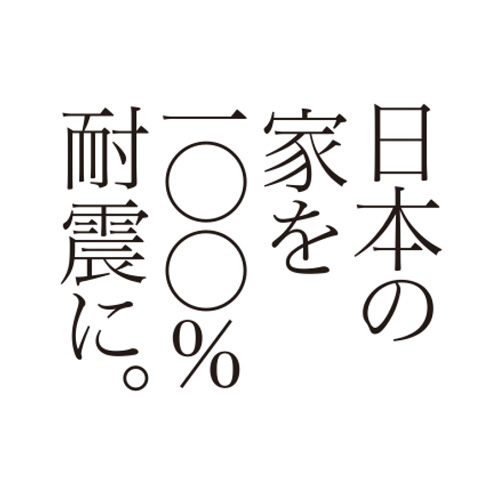都市の狭小角地に建つこの住宅は、天空率を活用して法的高さ制限をクリアしながら最大限のボリュームを確保。限られた敷地の中でも、2階の大きな開口部と勾配屋根が光と風をしっかり取り込む構成になっており、外部との適切な距離感を保ちつつ、開放的な暮らしができる設計。また、ファサードのシンプルな黒のサイディングが街並みに調和しながらも個性を主張しており、住まい手のライフスタイルや価値観を自然と表現します。小さなスペースにもゆとりを感じるこの住まいは、「都会に暮らす」ことの豊かさと心地よさを実感できる住空間。







南側の連続窓からやわらかく光が差し込むリビングは、周囲と距離を保ちつつ、内に開く心地よい場所。高さを抑えた窓配置が、視線の抜けと落ち着きを両立。テレビ背面の間仕切り壁は、階段との緩やかなゾーニングを生み、空間に奥行きと変化をもたらします。空間の設計はあくまで余白を大切にし、家具はお施主さまのセンスが引き立つキャンバスのような存在。

限られた敷地だからこそ、空間のつながりと視線の抜けを意識して設計。階段・テレビ・ダイニングをひとつながりにレイアウトし、住まい全体が一体感をもって呼吸するような空間構成。コンパクトな間取りの中でも、窓からの光とグリーンが日常に彩りを添え、「狭さ」ではなく「近さ」や「心地よさ」を感じられる住まい。



キッチンとつながるダイニングは、暮らしの中心にふさわしい場所。南面の窓からたっぷりと光が入り、家族や仲間が自然と集まりたくなる空気感がこの空間には漂う。そして、窓下に美しく納まる壁面収納やキッチン前カウンターは、お施主さまのご友人である家具職人さんが手がけた一点もの。天板の高さや照明の配置も細やかに設計し、食べる・語らう・手を動かす——そんな日常の動作が自然に流れる場。

動線と収納のバランスを丁寧に設計したキッチン。壁一面にタイルをあしらい、清潔感と奥行きを演出しながら、見せる収納と隠す収納を適所に配置。シンクと加熱機器の配置はシンプルながら、調理・片付けの流れが自然に完結するよう工夫されており、使うたびに心地よさを実感できるつくりに。



天空率によって生まれた斜めの天井が印象的なこの空間は、3階の子ども部屋。高さの制約はあるものの、それがかえって包まれるような安心感を生み出し、まるで“ひみつ基地”のような特別な居場所。構造梁をあえて見せた仕上げは、木のぬくもりとリズムが空間に遊び心を添え、自然と創造力が刺激されるような雰囲気。

勾配屋根の形状に合わせて設けた高窓から、自然光が穏やかに差し込む子ども部屋。日中は照明に頼らずとも、心地よい明るさが空間をやさしく包み込む。光の取り入れ方ひとつで、「居たい」と思える空間。

兄の部屋は扉で仕切れる個室。限られたスペースながら、勾配天井の低い側をベッドスペースに充てることで、落ち着きと居心地の良さを両立。書斎コーナーや収納もコンパクトにまとめ、“こじんまり”の中に集中と安心が共存する空間。



室内の印象を大きく左右する階段には、鉄骨フレーム✕木製踏板のスケルトン階段を採用。無駄を削ぎ落としたシンプルな構成が、空間に凛としたリズムを与え、軽やかに上下階をつなぐ。黒皮調の鉄部は視覚的なアクセントとなりながらも、過度に主張せず、周囲の素材との調和を大切に。その潔い佇まいは、家全体の設計思想を象徴する存在でもある。

鉄骨階段に組み合わせたのは、無垢材の手すり。スチールのシャープな印象に、手のひらになじむ木のあたたかみ感じる。シンプルな断面とスムーズな納まりにより、視覚的な軽やかさと安全性の両立を実現。上り下りのたびに、自然素材の心地よさを手で感じることができる。

窓まわりには、断熱性と美しさを兼ね備えたハニカムブラインドを採用。蜂の巣状の構造が空気の層をつくり出し、夏は熱を遮り冬は暖かさを保つ、小さくて頼もしい建築的ディテール。素材のやわらかさと透け感が、光を拡散しながらやさしく室内を包み込み、木枠との相性も上品に。快適さと意匠性をそっと両立させたブラインド。

お施主様がこだわって選ばれたペンダント照明。潔くシンプルなデザインながら、灯りの広がりや影の出方まで計算された存在感。点灯すると、やわらかな光が壁を伝って広がり、空間全体にやさしい陰影をもたらす。明るさ以上に、“雰囲気”を丁寧に整えるための灯りとして、この住まいにしっくりと馴染んでいる。

シェード越しに広がる淡い光が、壁や天板にそっと滲むこの照明は、Flame社の「cotton lamp(コットンランプ)」。リネン生地の質感を活かしたシェードと、手仕事を感じる陶器のベースが、空間にやさしい揺らぎと温もりを添えてくれる。明るさそのものよりも、「どんなふうにそこに居られるか」を整えてくれるあかり。お施主さまが丁寧に選んだこの一灯が、住まいの時間をより豊かなものに。

リビングの主役には、TRUCK FURNITURE社の「FK SOFA」と「IB COFFEE TABLE」。どっしりとした佇まいと、時を重ねるほどに深まる素材の味わいが、空間に芯のある落ち着きをもたらしている。住まい手の「これが好き」に、空間が静かに応える——そんな関係を大切にしたリビング。
建築概要
- 設計担当
- 千知岩賢二 鳴瀬加奈子
- 建築概要
- 耐震構法SE構法3階建て
- 建築面積
- 42.88m2(12.97坪)
- 延床面積
- 104.02m2(31.47坪)
- 施工面積
- 115.89m2(35.06坪)
- 敷地面積
- 63.4m2(19.18坪)
- 建ぺい率
- 67.64%
- 容積率
- 164.06%
- 耐震等級
- 等級3(最高等級)
- 耐風等級
- 等級2(最高等級)
- 断熱等級
- 等級6
- 温熱地域区分
- 6地域
- 年間日射量地域区分
- A4区分
- 用途地域
- 第二種住居地域
- 防火地域
- 準防火地域
- 耐火構造
- 準耐火構造
住まいの省エネ性能
省エネ性能測定値
- BEI
- 0.59
- 年間冷暖房負荷
- 216.66 MJ/(㎡・年)
- UA値(外皮平均熱貫流率)
- 0.42 W/㎡・K
- Q値(熱損失係数)
- 1.61 W/㎡・K
- C値(相当隙間面積)
- 0.5 c㎡/㎡
- ηAH値(冬の日射熱取得量)
- 0.8
- ηAC値(夏の日射熱取得量)
- 1.7
弊社基準値:UA値0.46W/㎡・K以下、Q値1.6W/㎡・K以下、C値0.5c㎡/㎡以下
年間光熱費比較
- 一般の家省エネ基準
- この住宅
- 27.61万円
- 17.9万円 35%節約
- 0
- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- ※基本料金なし、電気:¥28/kwh、ガス:¥150/m2 、売電単価¥16/kWh(2023年度)
- ※一般の家の省エネ基準は「H28年度省エネ基準」の性能値です
共通仕様
| 製品 | 熱貫流率 | 熱損失 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 断熱 | 屋根 | 外側 | 硬質ウレタンフォーム2種2号 36mm | 熱貫流率 0.22W/㎡K | 熱損失 10.93W/K |
| 内側 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 120mm | ||||
| 壁 | 内側 | 高性能グラスウール16K 120mm | 熱貫流率 0.36W/㎡K | 熱損失 78.73W/K | |
| 外気に接する床 | 内側 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 140mm | 熱貫流率 0.3W/㎡K | 熱損失 3.82W/K | |
| バルコニー直下の床 | 内側 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 180mm | 熱貫流率 0.25W/㎡K | 熱損失 0.63W/K | |
| 基礎 | 内側 | 硬質ウレタンフォーム2種2号 36mm | 熱損失 18.78W/K | ||
| 開口部 | 窓 | 樹脂複合防火サッシ|Low-Eペアガラス | 熱貫流率 1.51〜1.73W/㎡K | 熱損失 129.07W/K | |
| 玄関扉 | 鋼製断熱防火扉 | 熱貫流率 1.9W/㎡K | |||
| 熱損失合計 42.15W/K ÷ 外皮表面積合計 304㎡ = UA値 0.42W/㎡K |
|||||
| 製品 | 備考 | |
|---|---|---|
| 空調 | ルームエアコンディショナー | 各居室エアコン |
| 換気 | 第三種熱交換換気(ダクトレス) | 比消費電力 0.11W/(m3/h) |
| 給湯 | ガス潜熱回収型給湯器 | モード熱効率 92.5% |
| 照明 | すべての機器においてLEDを使用 | |
| 創エネ | なし | 太陽光パネルの搭載なし(光害抑止のため) |
一次エネルギー消費量
| この家の設計一次エネルギー | 基準一次エネルギー | 削減率 | |
|---|---|---|---|
| 暖房設備 | 17999MJ | 27316MJ | 34.11%削減 |
| 冷房設備 | 4851MJ | 10479MJ | 53.71%削減 |
| 換気設備 | 1740MJ | 3932MJ | 55.75%削減 |
| 給湯設備 | 16698MJ | 23605MJ | 29.26%削減 |
| 照明設備 | 5183MJ | 14480MJ | 64.21%削減 |
| 調理その他家電設備 | 20479MJ | 20479MJ | 0%削減 |
| 発電設備の発電量のうち自家消費分 | - | - | - |
| コージェネレーション設備の売電量に係る控除量 | - | - | - |
| 売電 | - | - | - | 66950MJ | 100291MJ | 33.2%削減 |
※基準一次エネルギーとは、住宅の省エネルギー基準における、地域や床面積などを考慮して定められた一次エネルギー消費量の基準値のことです。